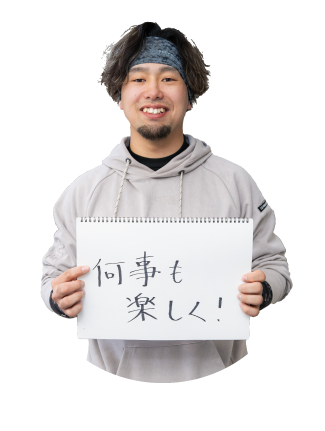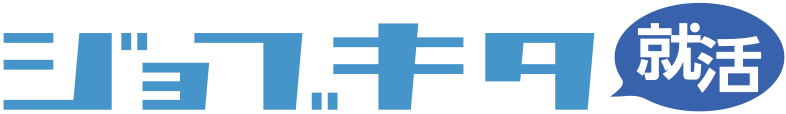インタビュー公開日:2025.05.19
- 幼いころに壁を塗った
楽しさを思い出しました。 - 左官という言葉を聞いたことがありますか?漆喰やモルタル、土といった素材を練り、コテと呼ばれる道具を使って壁や床を美しく仕上げたり、あるいは塗装やタイル貼りのための下地をキレイに整えたりする仕事です。
「高校生のころは体を動かす仕事がしたいと漠然と考えていました。実は、うちの社長と僕は偶然にも出身校と担任の先生が同じ。『建設業界で働いている卒業生がいるから話を聞いてみないか』と紹介してもらったんです」
こういって笑うのは株式会社鈴木工業所の左官工、中田弘大さん。当時は建設業界といっても大工しか知らず、さまざまな専門職が協力して工事を進めていることを初めて知ったと振り返ります。
「社長は左官に肩入れするのではなく、建設業界全体の話を聞かせてくれました。ただ、お世辞抜きに魅力を感じたのが左官工。子どものころ、親が家を建てた時に、壁を塗ってくれたのが父の知り合いでした。僕にも少しだけ手伝わせてくれ、幼心に楽しかったことを思い出したんです」
中田さんは左官の技術を身につけるのはやりがいがあると感じ、鈴木工業所に就職しました。

- 入社後1年間は訓練校で
左官の基礎を身につけます。 - 鈴木工業所では、未経験の新人が入社した1年間「札幌左官高等訓練校」に通い、左官の「さ」を学んでもらっています。
「4月はビッチリと訓練校に通い、ひたすら壁を塗っていくトレーニングを繰り返しながら基本動作を体に染み込ませていきます。その後は社内で現場作業の手伝いをしながら、月に2回ほど実践と講義を受けるイメージ。12月から3月までは、材料を混ぜ合わせる比率や建設業界の知識といった座学が中心となり、最後に卒業試験を受けるのが大まかな流れです。ちなみに、マジメに授業を受けていれば、大半の人は合格できます」
左官工というと職人の世界に思われがちですが、鈴木工業所では若い世代にも積極的に手を動かしてもらう指導スタイル。中田さんも、比較的早い段階からコテを持つようになったそうです。
「昔は2〜3年はコテを持たせてもらえなかったようですが、左官の面白さは何といっても塗ること。最近は外壁に補修材を塗ってキレイにするなど、難易度のさほど高くない仕事は新人さんにもどんどんトライしてもらっています」

- コテを使って塗ることで、
見栄えの良い建物へ! - 鈴木工業所では、壁を美しく塗り上げる「仕上げ」に携わることもありますが、学校やマンション、工場などの床や壁、階段などをキレイに形作る「下地」の作業が多いそうです。
「僕が最初に携わったのは10階建てのマンション。塗ってみては先輩のチェックを受け、修正してはまたチェック…というのを繰り返しながら1年半ほど現場に通いました。マンションの場合は型枠大工という職人がコンクリートで建物の基礎となる壁や床を作りますが、そのままでは凸凹や傾斜があったりするんですね。そこで、僕らの出番。壁紙をキレイに貼れるようにコテで表面を滑らかに整えたり、床を平らにしたり、見栄えの良い建物へと仕上げていきます」
左官で使う材料は水を使って練っているため、乾いてしまうと固まって手の施しようがなくなってしまうのだとか。新人時代は「柔らかさを確かめながら仕事をしろ」と何度も注意されたと苦笑します。
「夏場は気温が高いので材料が固まりやすく、冬場は逆に時間がかかります。季節による違いを考えながら、効率よく作業を進めるのも大切です」

- ミリ単位の調整が難しく、
だからこそ楽しいんです。 - 中田さんは、入社から3年ほどで一人立ちし、現在は8年目。大規模な工場建設の現場でも職長として若手をとりまとめています。
「入社当初は材料をコテにのせるだけでも難しく、少しずつ経験を重ねるたびにできることが増えていきました。僕自身は仕上げにこだわるのが好きで、例えば窓際を数ミリ厚く塗ってしまうだけでサッシを取り付ける際に不格好に見えたり、階段の幅がほんの少し狭いだけでも人が転んでしまう可能性が高くなったりします。ミリ単位の調整が難しく、だからこそ面白い世界です」
こう聞くと、中田さんご自身は器用なタイプに思えますが、意外にも「特別に器用なワケではなかったから最初は不安だったんですよ」と表情を引き締めます。
「左官の技術は経験すればするほど高まっていきますし、失敗してもカバーするから安心してチャレンジしてもらえる環境を整えているのも当社の魅力。若手には器用さだけがすべてではないと、よく伝えています」

- 「塗って楽しい」を
若い世代にも知ってほしい! - 建築物の現場では多種多彩な専門職が細かく分かれて一つの建物を作り上げています。その中でも左官工は、工程のほぼ最初から最後まで作業しているのが特徴なのだそうです。
「例えば、大工は骨組みを手がけたら次の現場へ移りますし、塗装工は最後のほうにしか立ち会えません。建物が少しずつ形になっていく姿を見届けられるので愛着が増しますし、『ココを削っておかないとドアが開かなくなる』など次の工程を考えられるようになるのも面白みです。入社したてのころは、完成後の建物をよく見に行っていました」
鈴木工業所には20代の若手も増えてきており、現場から事務所に帰ってくるとついつい話し込んでしまう日も多いとか。この明るい雰囲気が会社に好循環をもたらしているといいます。
「うちの会社では2時間程度の壁塗り体験も行っています。中学生でも高校生でも、保護者の方とご一緒でも良いので、まずは『塗って楽しい』を知ってもらいたいですね」

- シゴトのフカボリ
- 左官工の一日
- 7:30
- 出勤/現場へ移動
- 8:00
- 現場作業
- 10:00
- 休憩
- 10:30
- 現場作業
- 12:00
- 昼休み
- 13:00
- 現場作業
- 15:00
- 休憩
- 15:30
- 現場作業
- 17:00
- 事務所へ移動
- 17:30
- 退勤



- シゴトのフカボリ
- 拝見!オシゴトの道具

- 左官工といえばコテ!
- コテと一口にいっても、塗る場所や使う材料によっていくつもの種類を使い分けています。当社では最初に基本の10種程度を揃えてもらいますが、自分の手になじむものを見つけていくのも面白いんですよね。
- シゴトのフカボリ
- みなさんへ伝えたいこと
株式会社鈴木工業所
「コテを使って仕上げ完成させる物は、全て左官工事である」のコンセプトにもとづき、塗床工事や防水工事、改修工事なども手がける左官のスペシャリスト集団。地場の顧客から信頼が厚く、創業100年も間近。

- 住所
- 北海道札幌市北区北22条西8丁目2-3
- 建物の居住空間を快適に
- 内装工
- 内装工とは
- 壁や床、天井など、
建物内部を美しく装う!
建物の居住空間を快適に仕上げるのが内装工の仕事。とはいえ、「内装」と一口に言っても、建物の枠組みにボードを建てつけて壁を作る内装下地の作業から、壁紙の貼り付けや壁面の塗装まで幅広い分野があります。そのため、各専門職が分業して仕上げまでの一連の作業を担うのが一般的。例えば壁に使用する下地をつくる「鋼製下地組立工」、木製や鋼製の下地にボードや合版を張る「ボード張り工」、壁紙を天井や壁面に貼る「壁装工」、コテを使い壁面などに壁材を塗り仕上げる「左官工」、床材の張り付けから塗装などを担当する「床仕上工」などが挙げられます。内装工の仕事は見栄えにも直結することから、技術の良し悪しが、建物の完成度を左右するとも言えるでしょう。
- 内装工に向いてる人って?
- 一つひとつの作業に責任を持ち、
デザインやセンスを磨き続けられる人。
内装工は建物の仕上がりを左右する仕事のため、一つのミスや手抜きが見た目の違和感に大きな影響を与えてしまうシビアな一面もあります。室内空間を美しく機能的に手がけるためには、使う人のことを想像しながら一つひとつの作業と向き合う責任感が必要です。また、デザインやセンスを磨き続ける勉強熱心な姿勢も求められるでしょう。体を動かすことが多い仕事なので、体力に自信がある人も向いています。
- ワンポイントアドバイス
- キャリアアップには、
「内装仕上げ施工技能士」!
内装工としてキャリアアップを目指す場合、国家資格「内装仕上げ施工技能士」の取得がオススメです。試験は共通科目の学科試験と、「プラスチック系床仕上げ工事作業」「鋼製下地工事作業」「ボード仕上げ工事作業」などから選ぶ実技に分かれ、それぞれ1級、2級、3級と難易度で区分けされています。この資格を取得することは内装工の技術の証となり、仕事の幅を広げていくためにも役立つでしょう。
この仕事の求人例