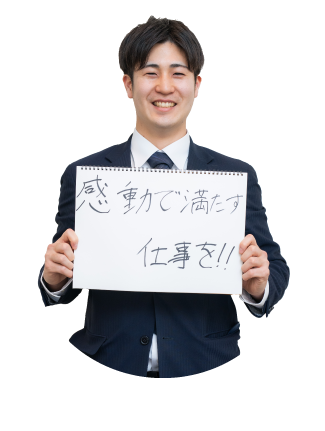インタビュー公開日:2025.07.31
- 好きだった歌手の曲を流すことも。
ご遺族とともに故人の人柄を伝える。 - 「お通夜は、『夜を通す』と書くように、故人に近しい人が集まって、お酒などを飲んだり、食べたりしながらひと晩、過ごす場。悲しむのではなく、思い出を語り合うことがお通夜のかたちなのだと、よくお寺さんは話されています」
そう教えてくれるのは、北海葬祭の松井彰良さん。同社は1937年の創業以来、90年あまりにわたって地域の葬儀を担ってきた、札幌の歴史ある企業です。「葬儀=悲しい」というイメージがありますが、仏教的な考え方では、現世から極楽浄土へと旅立つ、ある意味で「慶事」ともいえるのだそうです。
「実際に、通夜・葬儀の打ち合わせの際、故人の思い出を語るご遺族に笑顔が見られることも少なくないんです。好きだった歌手がいれば、CDを借りてきて出棺の際に曲を流すこともあるんです」
応援していたサッカーチームのユニフォームをマネキンに着せて飾ったり、たくさんの写真を集めて「思い出コーナー」を設けたり。ご遺族とともに、故人の人柄に触れてもらえるような通夜・葬儀になるよう、心遣いをすることが何よりも大事。まっすぐに前を向いてそう話す松井さんです。

- 友人の葬儀で、担当者の心づかいに感嘆。
大きな意義を持つ仕事であることを知る。 - 入社4年目にして、ベテランのエンディングプランナー(※)の風情も感じられる松井さん。実は同社は、松井さんの父親が代表をつとめる葬儀社です。ただし、松井さん本人は葬儀の仕事に就くこと、ましては入社することも考えていなかったのだとか。目指していたのは、プロサッカー選手です。
「高校、大学はサッカーの強豪校に所属し、全国大会の常連でした。そして、大学卒業後のプロチームとの契約を目指し、練習に励んでいました。そんな矢先、大学4年生の時に試合中のプレーで大きなケガをしてしまい……。選手としては見切りをつけました」
リハビリを経てリーグ戦の最終戦で復帰、優勝して全国大会に行きましたが、プロの道は断念。そこにはケガのほか、松井さんの気持ちを今の仕事へと向かわせるきっかけとなる、大きなできごとがありました。
「大学3年生の時、仲の良かった友人が病気で突然亡くなったんです。大きな悲しみのなか、この大切な人を送る葬儀に心を打たれたんです。葬儀の会場は当社。その時の担当者に、親族でもない私もとても良くしていただき、弔辞まで読ませてもらって。その担当者が、今の上司です」
父親が手がける仕事に大きな意義があることを、初めて知った瞬間でした。
※エンディングプランナー:葬儀をトータルにコーディネートする専門家

- 8カ月に及ぶ研修で基礎をじっくり学ぶ。
家族葬から社葬まで月に6、7件を担当。 - 仕事として正面から向き合うため、父親の前で正式に入社を懇願したという松井さん。親族だからと特別扱いはなし。一般の新卒採用とまったく同じ条件、環境での入社。葬儀についての知識もなく、ゼロからのスタートでした。
「入社から8カ月間は、びっしりと学びの時間でした。先輩について通夜の運営を補助したり、ご遺族との打ち合わせに同席したり。エンディングプランナーとしての業務とその流れ、役割などを現場で学んでいきました。また、葬儀の歴史といった、葬儀社のスタッフとして必要な知識を自ら勉強しつつ、ご遺族からの質問に対する先輩の受け答えなどを見ながら、実践のヒントをつかんでいった感じです」
葬儀終了後に、僧侶が語る「法話」にも学ぶところが多かったと松井さん。北海葬祭では、全宗教・全宗派の葬儀に対応しているため、それぞれの勉強にも取り組んできました。
「葬儀社は年配のスタッフが多いイメージがあるようですが、当社では20代、30代が多く活躍しており、どんなことでも気軽に聞けたのは、とても助かりました」
研修を通して一人前に育てるというのが、同社の方針。5名の家族葬から、400、500名が参列する社葬まで、月に6、7件の葬儀を担当するそうです。2年目には、葬祭ディレクター技能審査2級も取得しています。

- お迎えから出棺までを1人が担当。
ご遺族からの信頼が何よりうれしい。 - 訃報を受けてのお迎えに始まり、打ち合わせ、翌日に通夜、その翌朝に出棺というのが、通夜・葬儀の一般的な流れ。このなかで、特に重要なのが最初の打ち合わせなのだそうです。
「通夜・葬儀の内容や進行を決めるために、まず、故人の家族構成、参列される人数の目安などを確認します。さらに、例えば故人の性格、趣味なども聞き取り、好きだった色で棺を仕立てるといった提案も行います。ご家族内の関係性や背景をある程度、理解しなければ式の準備を的確にできないんです」
打ち合わせは2時間ほどかけてじっくり行うそうですが、そこで担当したスタッフはその後の通夜・葬儀まで付き添うというスタイルを取っています。だからこそ、ご遺族の思いに寄り添うことができるのだと松井さんは話します。
「葬儀が終わってご自宅に戻られる際にお花を届けたり、四十九日法要まで白木位牌を、正式な本位牌に作り直すといったアフターサービスも行っています。なかには、葬儀を無事に終えられた安心感から、涙を流して喜ばれるご遺族もいらっしゃいます。そんな姿を見ると、『頑張ったな』と力が湧いてくるんです」
以前、担当したご遺族から携帯電話に直接、新たな葬儀の依頼が入ることも。信頼してもらえている。そんな実感を得ることがうれしいのだと話します。

- 葬儀の現場の管理から式場のメンテナンス、
スタッフのメンタルケアにも携わる。 - 松井さんは現在、通夜・葬儀も担当しつつ、「営業推進室」という部署で葬儀の現場を管理する仕事も行っています。葬儀社としての同社の運営を、陰ながら支えるといった役割です。
「営業部門の責任者として、当社が運営する3つの斎場のメンテナンス、各斎場の人員配置や葬儀のスケジュールの管理、仏衣・棺ほか備品の新規導入も担っています。葬儀業界も時代とともにトレンドが変わるため、それらに対応するための環境整備ですね」
営業的な動きでは、病院や高齢者施設などの運営母体への提案も担当しているという松井さん。スタッフの採用やメンタルケアといった人的サポートにも力を入れています。
「葬儀社によっては、打ち合わせ・通夜・葬儀を分業で行うところもありますが、1人の担当者が付きっきりでサポートする当社のスタイルは、ご遺族が第一という観点から、変えたくないと思っています。そのために、社員教育には特に力を入れているんです」
早くも、その言葉には経営的な視点も感じられる松井さん。葬儀業界はハードルが高そうと、敬遠される傾向もあるなか、若い世代が多く、社員同士の仲が良い環境があることもアピールしたいと力を込めます。葬儀のイメージを、きっと変えていく一人になりそうです。

- シゴトのフカボリ
- エンディングプランナーの一日
- 8:50
- 出勤、朝礼
- 9:00
- 斎場の準備、ホールの準備
- 12:00
- 当日の流れ、通夜振る舞いの人数などをご遺族に最終確認
- 15:00
- 湯灌・着せ替え、納棺
- 17:00
- 通夜開始
- 19:00
- 通夜終了、退勤



- シゴトのフカボリ
- みなさんへ伝えたいこと
北海葬祭株式会社
1937年、札幌市で創業。市内に3つの斎場と生花部門をもち、祭壇にはすべて生花を使用。専任のスタッフが24時間対応し、地域の葬儀を担っています。

- 住所
- 北海道札幌市中央区南26条西14丁目1-15
- TEL
- 011-561-3344
- 要望に添ってご葬儀をサポート。
- セレモニープランナー
- セレモニープランナーとは
- 故人様を無事にお見送りできるよう、
葬儀全般をコーディネート。
セレモニープランナーはご葬儀全般のプランを組み立て、式場の準備や弔いの儀礼を支えるのが主な仕事。(故人様のご遺族や病院、警察からの訃報を受け、まずは故人様の安置や納棺の儀式を行います。その後は喪主と打ち合わせた上で、要望に添って祭壇の設営や火葬場・車両・料理・返礼品の手配、お通夜とご葬儀の司会進行、弔問客の誘導などをサポート。ご臨終直後から喪の儀礼をコーディネートし、故人様を無事にお見送りできるようにお手伝いします。
- セレモニープランナーに向いてる人って?
- 細やかな心遣いができ、
冷静な判断力とチームワークに長けた人。
ご遺族は悲しみや動揺に包まれているため、細やかな心遣いと思いやりを持ちながらも、冷静に対応できる人が向いているでしょう。病院や火葬場との連携が必要とされることから、調整力やスケジュール管理なども重要なスキルです。進行役や会場準備係、司会とチームワークを密にとれるコミュニケーション能力も求められます。
- セレモニープランナーになるためには
セレモニープランナーになるために特別な資格や学歴は必要ありません。ただし、葬祭業界を目指すための専門学校(学科)もあるため、就業前に宗教の知識や実習経験を積んでおくのもおすすめですが、未経験でも大丈夫。ご遺族の自宅への訪問や斎場への送迎といった業務もあることから、普通自動車免許の取得が必要です。
- ワンポイントアドバイス
- 「葬祭ディレクター技能審査」は、
ご葬儀をプランニングできる証。
セレモニープランナーとして実務経験を積むことで、厚生労働省認定の「葬祭ディレクター技能審査」の資格にチャレンジできます。2級は実務経験2年以上(または葬祭ディレクター技能審査協会が認定した教育機関のカリキュラムを修了)、1級は実務経験5年以上で受験資格を得られます。いずれも学科試験と実技の両方が問われる試験です。2級は「個人葬」、1級は「社葬」までプランニングできる証となります。
※「葬祭ディレクター技能審査」については、詳しくは葬祭ディレクター技能審査協会のホームページをご確認ください。http://www.sousai-director.jp/
この仕事の求人例
この仕事のほかのインタビュー。
ほかにもあります、こんな仕事。