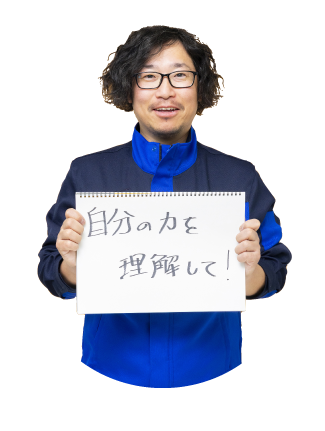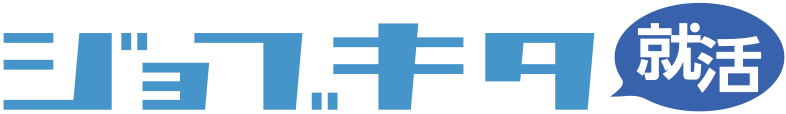インタビュー公開日:2025.04.17
- 電気を届けるために
欠かせない役割の職業。 - 旭川市の北東に位置する愛別町で電気の内線工事や発電所・変電所の保安・整備を行っているのが、今回取材に訪れた太洋電設株式会社です。会社にお邪魔してみると、まるで親戚の家に遊びに来たかのように賑やかな社内。先輩たちから「ミカちゃん」の愛称でイジられている三ヶ田(みかた)浩樹さんに、電気工事士という職業について詳しく伺っていきます。
「弊社では一般的な住宅や商業施設の内線工事と、発電所・変電所の点検・設備工事の2つを主に手掛けています。いずれもみなさんの生活になくてはならない『電気』を使うために必要不可欠な工事で、自分は主に変電所を担当しています」
ところで変電所の役割とは何ですか…?
「ですよね(笑)。水をイメージしてもらうと分かりやすいのですが、井戸から湧き上がった水を遠くまで運ぶためには、太いパイプと圧力をかけるポンプが必要ですよね。そうやって送られてきたのが高電圧の電力。ただそのままの圧力で一般の家庭へ流すと、勢いが強すぎてあふれてしまいます。だから、その勢いを『変電所』というバルブで調整する必要があるんです」
なるほど、とっても分かりやすい説明です。では具体的にどんな工事をしているのでしょうか?
「まずは定期的な点検で故障や劣化がないかをチェックして、おかしな配線や基盤は交換するというのが1つ目の役割。2つ目は、変電所が管轄する地域に新しい建物ができたり、逆に無くなったりした時です。例えば大きなショッピングセンターが建つとしたら、その地域の電気の使用量が一気に増えますよね。そうすると設備を大きくしたり、新たに機械を追加する必要があるんです」

- 電気工事士になったのは
年賀状のおかげ? - 会社の中堅として今ではテキパキと働く三ヶ田さんですが、電気工事士になるまでの道のりは一直線ではなかったのだそう。旭川工業高校で電気について学んではいたものの、卒業後は職を転々としていたそうで、太洋電設で働き始めたのは23歳の頃、郵便局の契約社員からの転職だったといいます。
「年賀状を買ってもらおうと母校・工業高校を訪ねたら、先生から『電気工事士の試験受けたらどうだ』と言われて、その後に軽い気持ちで試験を受けたらなんと合格しちゃって…(笑)」
その後、求人誌を見て電気工事系の会社で唯一「経験不問」と書かれていた太洋電設に応募したという三ヶ田さん。入社後は住宅や商業施設といった内線工事の現場で、先輩のサポートからスタートしたそうですが、電気工事士の「何でも屋」ぶりには当初、戸惑いを覚えたといいます。
「配線をいじるだけじゃなくて、線を通すために壁や天井を剥がして穴を開けるといった内装屋さんのような作業をしたり、線を通すための建具を取り付ける大工仕事があったりと、思った以上に業務の幅が広かったんです」
ただ、こうした作業から覚えていく教育スタイルはとても勉強になったと振り返ります。
「電気の仕事は危険と隣り合わせです。はじめはさまざまな不安がある中で、先輩たちがいかに安全対策をしているか、どんな所に気をつけているのかを間近で見られたのは安心できました。あと色々経験したおかげで今ではテーブルや椅子を作れるくらいのDIYの能力も身についています(笑)」

- 安全のためには、
視野の広さと仲の良さが大切。 - 入社当時を振り返り「自分は先輩たちからかなり過保護に育てられた」と笑う三ヶ田さん。部下が困るといつでもフォローに駆けつけ、新人の意見も聞き入れてくれる先輩たちはとても大きな存在で、この頃の思い出は今も三ヶ田さんの礎(いしずえ)となっているのだそうです。
変電所や発電所の現場へ行くようになったのは入社から3年ほど経ってからのこと。事前に滝川市にある他社の社員研修所でも勉強や練習を重ね、さらに業務に必要な資格は会社のフルサポートのもと取得していきました。
「意外に思われるかもしれませんが、低電圧を扱う内線工事も高電圧を扱う発電所・変電所の現場も、さほど危険性は変わりません。自分だけでなく仲間たちも守るために常に『安全第一』を心がけ、危険を察知したらすぐに声をあげること、広い視野を持って周囲を冷静に観察することが大切です」
現場では20mクラスの鉄塔に登ることもあり、重い工具を身につけての作業は体力も必要ですが、常にチームで声を掛け合いながら互いに支えあっているそうです。
「この業界といえば『無口な職人さん』が多いのが常識ですが、ウチは見ての通り、とにかく賑やかで先輩たちのキャラが濃い(笑)。もちろん仕事中では真剣そのものですが、日ごろの仲のよさが現場でのちょっとした気づかいや、いざという時のチームワーク、危険から身を守るための意識に発揮されていると実感しています」

- 被災地の支援や
環境問題解決にも関わるやりがい。 - 社会になくてはならない電力インフラを守り続ける太洋電設の仕事。三ヶ田さんの仕事のフィールドは広範囲に及び、旭川市内の変電所を中心に、稚内や北見など道北や道東方面まで出張することもあります。近年では再生可能エネルギーの普及に伴い、仕事の内容も変化してきているのだそうです。
「最近では太陽光発電パネルや蓄電池の設置工事なども増えてきましたし、発電所も環境負荷の少ない水力や風力の活用が増えてきていて、僕たちの仕事も少しずつ変化していると実感しています。微力ではありますが、環境問題解決の手助けもできているかもしれません」
また2018年の北海道胆振東部地震で大規模停電(ブラックアウト)が発生した際には、真夜中に発電機を積んだ車両を走らせ、被災地に電気を届けるという重要な役割も担いました。
「真夜中の作業ではありましたが、地域の方々から感謝の言葉を頂けて、自分たちの仕事が役に立っているとヒシヒシと実感した瞬間でした。ニュースやラジオで『あんな大変なことがあったね』と話題が出るたびに、『今ちゃんと使えてるのは自分たちのおかげだぞ』って、心の中でつぶやいています(笑)」

- モチベーションは
電気を守る使命と帰宅後のビール! - 仕事のモチベーションについて「働いたことに対してちゃんと評価してもらい、それに見合った報酬をもらえること」と話す三ヶ田さん。昭和の風潮を残したままの働き方も少なくない電気工事業界ですが、太洋電設では働き方改革に積極的に取り組み、給与は同業他社と比べても高く、残業をしないよう徹底。近年は完全週休二日制も実現し、福利厚生にも力を入れています。
「経営が苦しいところも少なくないと聞きますが、弊社はほくでんグループが管理する発電所・変電所を守る使命を担っているので、経営上安定しています。だからこそ福利厚生やお給料がきちんとしていて、小さな会社ですが大企業にも決して引けを取らない環境です。電気を届けるには、自分たちのような会社の存在が必要不可欠ですから、電気工事士は将来AIがどれだけ発達しても、代わることができない職業だと思います」
最後に、学生のみなさんにアドバイスを求めると「どんなに綺麗事を言ってても、働く上での安心感や生活を充実させるためのお給料はかなり大切です」と話します。
「やりたいことがない人は、たとえ未知の世界でも挑戦して、実際に手を動かしてみると見えてくるものがあります。僕はデスクワークが苦手なので、こうやって身体を動かしてお金を貰って、帰ったら美味しいビールを飲む。単純かもしれませんが、それだけでけっこう幸せです(笑)」

- シゴトのフカボリ
- 電気工事士の一日
- 8:00
- 出勤、荷物を積み車へ
- 8:30
- 現場に到着後、朝礼・KY(危険予知)ミーティング
- 9:00
- 作業開始
- 10:00
- 小休憩(10〜15分)
- 12:00
- 昼休憩(1時間)
- 13:00
- 作業開始
- 15:00
- 小休憩(10〜15分)
- 16:30
- 片付け、帰社
- 17:00
- 退勤



- シゴトのフカボリ
- みなさんへ伝えたいこと
太洋電設株式会社
愛別町にて1952年(昭和27年)創業の電気設備工事会社。旭川・上川エリアを中心に、一般住宅から公共施設、通信設備などの電気工事、発電所・変電所の保守・点検、変電設備の据付・組立まで幅広く手がけている。

- 住所
- 北海道上川郡愛別町字本町255
- TEL
- 01658-6-5527
- 電気設備のエキスパート。
- 電気工事士
- 電気工事士とは
- 電気設備の設計から
施工までを担う技術者。
電気工事士の仕事は、大きく「建築電気工事」「鉄道電気工事」「発電所・変電所工事」に分かれます。建築電気工事とは、一般住宅やビル、工場、商店などの建設現場で、屋内外の電気設備の設計から施工までを担うのが主な業務。現場に合わせて電気配線図面を作成し、他業種と連携しながら配線や配電盤の据え付けを行います。鉄道電気工事は、駅・鉄道関連施設の電気設備の点検やメンテナンス、架線(電線)の張替えなどによって、電車の安全な運行を支えるのがメインです。発電所・変電所工事は、電力の生産・供給を支える重要なインフラ設備の建設・保守を担当し、高圧・超高圧電気設備の据え付けや点検、送電線の架設・保守などを行います。電気を扱う工事は危険も多いため、国家資格「電気工事士」の取得が必須条件。「第一種」と「第二種」があり、第一種はビルや工場など、第二種は一般住宅や小規模の店舗など、それぞれ異なる規模の建設現場を担います。
- 電気工事士に向いてる人って?
- コツコツと作業を進められ、
慎重さも兼ね備えている人。
電気工事士は職人的な技術が必要とされる仕事。納期を守りながら安全かつ正確に作業を進めていくことが重要なことから、集中力をキープしてコツコツと作業に没頭できる人に向いているでしょう。時に危険を伴う作業もあるため、確認を怠らずに仕事を進める慎重さも必要です。また現場での据え付け工事は、他業種の職人と連携しながら作業を進めることも多いため、円滑にコミュニケーションができる人にも適正があります。
- 電気工事士になるためには
電気工事士の仕事に就く上で、学歴は問われないことが多いようです。まずは国家資格「第二種電気工事士」を取得するのが第一歩です。大学や短大、専門学校などで電気工学や通信工学、機械工学などを学んでおくと、資格取得がよりスムーズになります。「第二種電気工事士」には受験に関する制限がなく、独学でも取得可能です。この資格があれば、有利に就職活動を進められるでしょう。なお、発電所・変電所工事の分野を目指す場合は、電力会社での専門的な研修プログラムが用意されており、高圧・超高圧電気設備の安全な取り扱いや特殊技術について学ぶことができます。
- ワンポイントアドバイス
- 電気工事士のニーズは常に高く、
ステップアップも目指せます。
電気は暮らしに欠かせないことから、電気工事士の仕事は常に社会から求められています。人手不足が心配される昨今では、業界を通じて次代を担う人材育成に力を入れており、会社が資格取得をバックアップする動きも見受けられます。電気工事士として経験を積んだ先には、国家資格「第一種電気工事士」や「電気主任技術者」を取得し、ステップアップすることも可能です。
この仕事の求人例
ほかにもあります、こんな仕事。