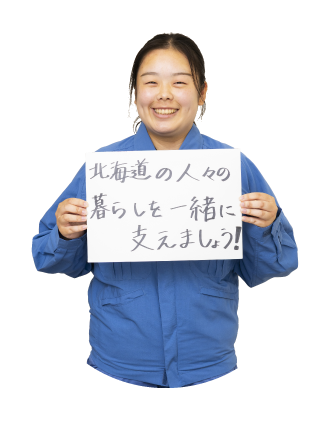インタビュー公開日:2025.09.02
- 電圧を調整して、電気を届ける設備、変電所。
その保守を通して、電気の供給を担う。 - 電気が発電所でつくられていることは、もちろん誰でも知っています。けれども、それがどうやって届けられているのか……となると、ちょっと説明が怪しくなります。発電所で生まれる電気は、18万7,000ボルト、27万5,000ボルトなどへと電圧を上げて送り出されます。そのままではユーザーは電圧が高すぎて使えないので、段階的に電圧を下げて、最終的には6,600ボルトにします。その役割を果たすのが変電所。その後、配電線を通じて運ばれ、電柱の変圧器で100ボルト、200ボルトに下げて家庭や施設に届きます。
「私はこの変電所を常に正常に機能させるための保守、点検計画などを担当しています。入社2年目を迎え、自分の仕事の重みをより実感するようになりました」
そう話すのは、『北海道電力ネットワーク』(以下、『ほくでんネットワーク』)の土川真歩さん。まだまだ、わからないことも多いと言いつつ、落ち着いた受け答えが印象的です。
「私が所属するグループが担当しているのは、道央圏に設置されている17の変電所。月の半分は、そのいずれかに出向いて業務を行っています。月ごとに出向する変電所や回数・作業内容などが異なることも、この仕事の特徴ですね」
大切な電気の供給の一端を担っている。そんな実感がやりがいなのだと、明るい笑顔のなか、自信も芽生えているようです。

- 3つの「巡視」を基本に変電所をまわり、
目視による点検や数値チェックを実施。 - 意外と気づきにくいですが、変電所は都市の街なかにもあります。普段の運用は遠隔操作で行われていますが、保守点検には人のチェックが必須。そこで、土川さんたちの出番というわけです。
「変電所には、変圧器などさまざまな設備があります。それらを目視で点検したり、設備の稼働を示す機器の数値をチェック・記録したりするのが私の仕事。異常があれば、機器メーカーさんとやりとりを行い、解決策や応急的な対応について協議することもあります」
保守業務は、現地へ赴いて行う巡視が基本。巡視には定期巡視・測定巡視・重点巡視の3つがあり、それぞれ対応内容や実施間隔が異なります。
「定期巡視は、3カ月に1回の間隔で17変電所すべてをまわり、機器のチェックを行ってきます。8人のスタッフが2人1組となり、手分けして行うこの巡視が、メイン業務ですね。基本となる巡視なので、とにかくしっかりと機器の状態などを見ていきます。測定巡視は年2回、3人1組で機器の数値を詳しく調べる巡視です」
もう1つの重点巡視とは、過去に異常が見つかった機器を毎月、重点的に監視する業務で、対象となる変電所に出向くというもの。さらに、変圧器などの電気的絶縁のために油が封入されている機器で漏油が発生した場合、補修を実施する等、実に多様な業務を担っています。

- 最北端の北海道から最南端の沖縄へ。
人の温かさを感じ、地元の良さを知る。 - 大学で電気工学を専攻した土川さん。しかし、札幌出身でありながら、4年間学び、過ごしたのは沖縄県の琉球大学でした。なぜ、最北端から最南端へ向かったのでしょうか。
「それほど立派な理由はなくて……。小さい頃から、沖縄に憧れていたというのが一番の理由でした(笑)。大学の4年間限定で、沖縄で暮らす経験がしてみたいなと思ったんです。感想? もう、めちゃめちゃ楽しくて!人の温かさを実感できた貴重な体験になりました」
沖縄の良さを実感しながら過ごした大学時代。その日々はまた、暮らしていた時には気づかなかった北海道の良さにも気づかされるきっかけになったと土川さん。就職にあたっては、地元で働きたいと自然に思えたのだそうです。
「北海道の暮らしを支えたい、そうした役割を担える仕事に就きたいという思いが、中心にありました。電気はまさに、その代表格。高校3年生の時に、ブラックアウトを引き起こした北海道胆振東部地震を経験し、電気の大切さを実感していたことも『ほくでんネットワーク』への入社を考える動機でした」
変電所に関わる仕事を意識していたわけではなかったものの、配属された今の部署では大学時代に学んだことを活かせる場面もあり、意欲をもって取り組める仕事に出会えたと、うれしそうに話します。

- 他部門の担当者との連携作業を通して、
途切れることなく電気を届けていく。 - 大学で身に付けた電気系の知識が役立つ場面も多い一方で、変電設備については入社後、一から学んできたことがほとんど。聞き覚えのない用語も多く、慣れるまでは少し大変さも感じたと振り返る土川さん。
「助けられたのは、職場の環境ですね。とにかく誰にでも話しやすい雰囲気があり、わからないことを聞けば、即座に教えてもらえました。それだけではなく、疑問が浮かんだ際の調べ方などを示してもらえたので、自ら学べるようになり、知識を身に付けていくことができました。また、1カ月半に及ぶ入社時の合同研修では、技術系の社員が部署を超えて共同生活を送りましたが、そこで生まれた同期の絆は今も支えとなっています」
実際の現場でも、他部門の担当者と連携する業務は多く、スムーズなコミュニケーションの基礎になっているのだと話します。
「例えば、変電所から電気を送る配電線の点検や修理が行われる場合、作業箇所の電気を止める必要があり、私たちが変電所に出向いて電気を止めるための機器を操作するんです」
しかし、作業中でも、電気自体の供給を止めるわけにはいきません。そこで、臨時の回路を確保するといった作業も土川さんの仕事。関係する部署と協力し合うことにより、日々、絶えることなく電気が届けられているのです。

- 視野の広い先輩の姿に学びながら、
後輩への指導を通して自らも成長。 - 「変電所の設備は何年に1回など、点検すべき周期が決められています。この点検作業に関しては、協力会社さんに依頼し、私たちは現場の安全、工程などの管理を行います。自分が計画して進めた作業が、トラブルなく完了した時には大きな達成感がありますし、『やりきった!』という感覚になりますね」
協力会社のスタッフの方も、段取りなどわからないことを尋ねると、丁寧に教えてくれるのだとか。親しみやすい土川さんのキャラクターも、場を和ませているようです。
「変電所のフェンスに木の枝がかかれば取り払ったり、変電所内や周辺で鳥が巣を作ると停電につながる危険性があることなどから撤去します。そんな多様な業務を自分の判断で進められるところにも楽しさを感じています」
目配りも大切な仕事と言えそうですが、先輩は視野が広く、自分が気づけないことにも注意を払っていると感心したようすで話します。その姿に学びつつ、今は後輩の指導も担当するようになりました。「後輩に教えることを通して必要な知識への理解が深まるなど『成長しているな、自分!』と最近、感じます。自画自賛ですが」と笑います。将来的には、変電所の工事にも携わってみたいという新たな意欲も。沖縄の風土で磨かれたという土川さんの社交性が、今日も社内を明るくしています。

- シゴトのフカボリ
- 電気技術者の一日
- 8:40
- 出勤、点検の準備(装備、車両の準備)
- 9:00
- 点検へ出発
- 9:30
- 変電所で停電作業の準備
- 10:00
- 協力会社との打ち合わせ、管理業務
- 12:00
- 昼休憩
- 13:00
- 点検の管理業務
- 16:30
- 業務終了
- 17:20
- 退勤
※業務内容・量によって出退勤時間は変動します



- シゴトのフカボリ
- みなさんへ伝えたいこと
北海道電力ネットワーク株式会社
北海道電力の送配電部門を分社化して2020年に設立。発電所から電気を送る送電、電圧を整える変電、電気を届ける配電を保守点検により守っています。

- 住所
- 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地
- TEL
- 011-251-1123
- 電気設備のエキスパート。
- 電気工事士
- 電気工事士とは
- 電気設備の設計から
施工までを担う技術者。
電気工事士の仕事は、大きく「建築電気工事」「鉄道電気工事」「発電所・変電所工事」に分かれます。建築電気工事とは、一般住宅やビル、工場、商店などの建設現場で、屋内外の電気設備の設計から施工までを担うのが主な業務。現場に合わせて電気配線図面を作成し、他業種と連携しながら配線や配電盤の据え付けを行います。鉄道電気工事は、駅・鉄道関連施設の電気設備の点検やメンテナンス、架線(電線)の張替えなどによって、電車の安全な運行を支えるのがメインです。発電所・変電所工事は、電力の生産・供給を支える重要なインフラ設備の建設・保守を担当し、高圧・超高圧電気設備の据え付けや点検、送電線の架設・保守などを行います。電気を扱う工事は危険も多いため、国家資格「電気工事士」の取得が必須条件。「第一種」と「第二種」があり、第一種はビルや工場など、第二種は一般住宅や小規模の店舗など、それぞれ異なる規模の建設現場を担います。
- 電気工事士に向いてる人って?
- コツコツと作業を進められ、
慎重さも兼ね備えている人。
電気工事士は職人的な技術が必要とされる仕事。納期を守りながら安全かつ正確に作業を進めていくことが重要なことから、集中力をキープしてコツコツと作業に没頭できる人に向いているでしょう。時に危険を伴う作業もあるため、確認を怠らずに仕事を進める慎重さも必要です。また現場での据え付け工事は、他業種の職人と連携しながら作業を進めることも多いため、円滑にコミュニケーションができる人にも適正があります。
- 電気工事士になるためには
電気工事士の仕事に就く上で、学歴は問われないことが多いようです。まずは国家資格「第二種電気工事士」を取得するのが第一歩です。大学や短大、専門学校などで電気工学や通信工学、機械工学などを学んでおくと、資格取得がよりスムーズになります。「第二種電気工事士」には受験に関する制限がなく、独学でも取得可能です。この資格があれば、有利に就職活動を進められるでしょう。なお、発電所・変電所工事の分野を目指す場合は、電力会社での専門的な研修プログラムが用意されており、高圧・超高圧電気設備の安全な取り扱いや特殊技術について学ぶことができます。
- ワンポイントアドバイス
- 電気工事士のニーズは常に高く、
ステップアップも目指せます。
電気は暮らしに欠かせないことから、電気工事士の仕事は常に社会から求められています。人手不足が心配される昨今では、業界を通じて次代を担う人材育成に力を入れており、会社が資格取得をバックアップする動きも見受けられます。電気工事士として経験を積んだ先には、国家資格「第一種電気工事士」や「電気主任技術者」を取得し、ステップアップすることも可能です。
この仕事の求人例
ほかにもあります、こんな仕事。